会長挨拶
日本希土類学会会長 九州大学教授 稲永 純二
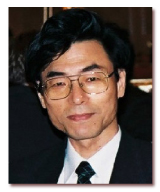
この度、足立吟也前会長の後を継ぎまして、第13期の日本希土類学会会長を拝命しました。就任にあたり、本会の目的や活動状況とともに少しばかりの抱負とお願いを述べさせて頂きます。
日本希土類学会は、1982年11月に希土類研究会として発足し、1995年に日本希土類学会と改名して今日に至っています。本会は、希土類に関心がある研究者、技術者、経営者が集い、希土類に関して何でも討論しうる場を提供することにより相互の知識を交換し、希土類の科学と技術を進歩向上させることを目的としています。
主な年間行事として、最新の研究成果を発表する討論会(5月)、若手研究者の育成に焦点を当てたサマースクール(8月)、第一線の研究者の話をじっくり伺うことができる講演会(11月)を開催しております。また機関誌「希土類 Rare Earths」を年2回刊行し、情報発信とともに会員相互の情報の交換の便を図っております。国際会議としては、1992年6月に「Rare Earths‘92 in Kyoto」を、また2004年11月に「Rare Earths‘04 in Nara」を主催しました。いずれの会議もこの分野では史上最大の規模と最高のプログラムと讃えられています。
希土類は周期表の中でも最大のグループであり、実に全元素の1割以上を占めています。最大の特徴は4f軌道を有するランタニド元素群を擁していることであり、磁気(磁石)、光(蛍光体、発光体)、エレクトロニクス(超伝導)、エネルギー(水素貯蔵、燃料電池)、触媒(排ガス浄化、医薬 品・高分子合成)、医療・生理学(診断、分析、バイオテクノロジー)など、その研究は多岐にわたっています。
したがいまして本会には、大学・国公立の研究機関や企業の研究所など様々な機関に所属する研究者が、物理、無機、有機、生物、錯体、材料など広い研究分野から集まっており、学際領域の研究や新研究領域の開拓を目指す研究者にとっては大変魅力的な極めてユニークな組織となっています。本会はまた、維持会員としての企業の貢献が大きいのも特徴で、学問的研究のみならず身の回りの製品開発に至るまで希土類について実に多くのことを学ぶことができます。これからも異分野・異業種との関わりの強さを活かして活力ある学会活動を展開し、是非会員諸氏のお役に立ちたいと思っています。会員の皆さまにおかれましては、討論会や講演会等への参加をとおして本会をよりいっそうご活用ください。また、会員以外で希土類に興味をお持ちの多くの皆さまの本会への積極的参加を心より希望しています。
本会が「希土類の科学と技術」の進展に大きな貢献ができますよう、皆さまのご支援ご鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。